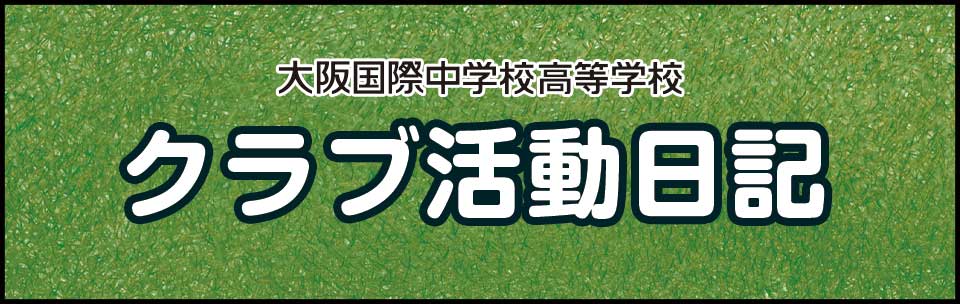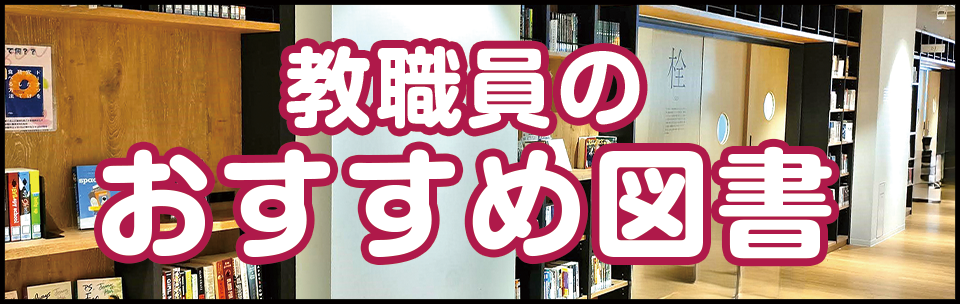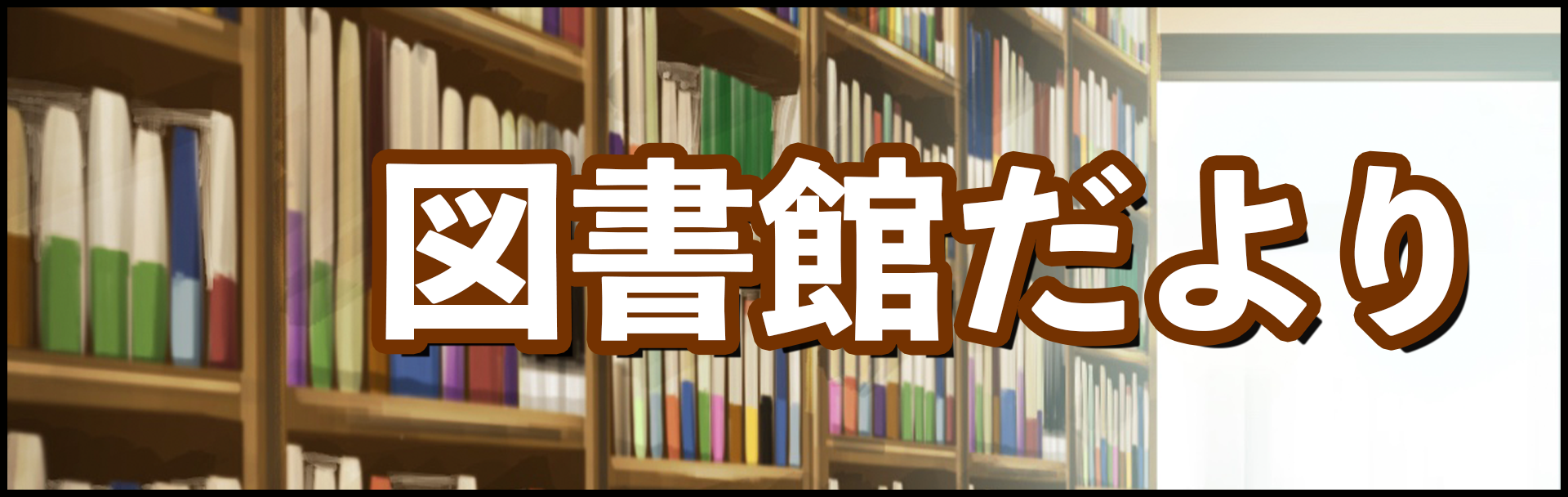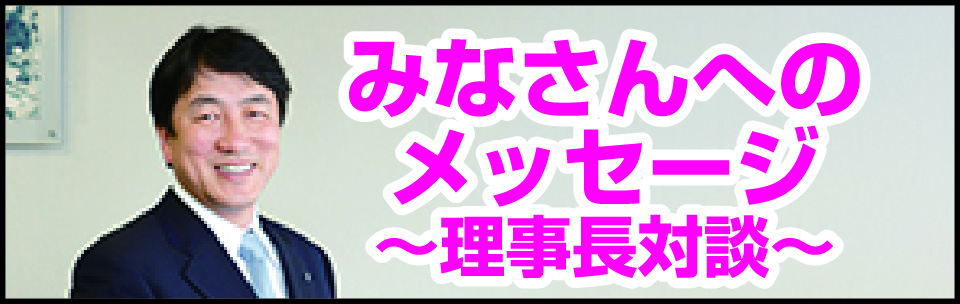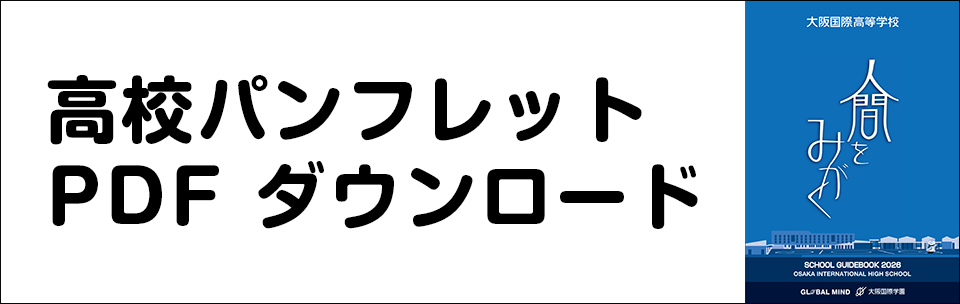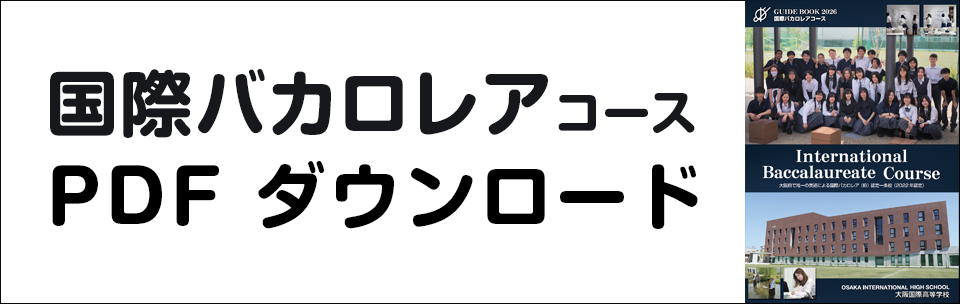未来に向かう子どもたちへのメッセージ、やりたいことに挑戦する道を進もう。
名古屋大学教授 天野浩氏
(2014年ノーベル物理学賞受賞)
様々な分野の著名人をお迎えして、みなさんにメッセージを贈っていただく理事長奥田の対談シリーズ第3弾。
今回お話いただいたのは、2014年に青色発光ダイオードを開発し、赤﨑勇博士・中村修二博士と共にノーベル物理学賞を受賞された、天野 浩氏です。
家や学校の蛍光灯、道路の信号機など、現代ではあらゆる場所で「LEDライト」が使われています。実はこのLEDライト、天野博士たちが開発した青色発光ダイオードによって、一般的に使用できるようになったのです。
そんな素晴らしい研究成果を上げた天野氏に、研究者になるまでにどんな道をたどってきたのか、お聞きしました。
悩みながらも道を選び、前へ進んできた天野氏のお話は、見どころ満載です。
悩み、考えたからこそ見つかった道。
現役で研究者として活躍しながら、大学で多くの学生への指導も行っている天野氏。まずは直近の活動から、そして研究者になるまでの半生について伺った。
2014年に青色発光ダイオードを開発して、赤﨑勇先生・中村修二先生とともにノーベル賞を受賞された天野さん。研究はもちろん講演会等でもご活躍されていますね。
ありがたいことに、様々なお仕事をいただいています。実は昨日も応用物理学会のシンポジウム※1に参加しました。そこで一つ気になっていることなんですが、講演会等で学生の方々から質問を受けると、研究テーマとは別に進路相談を受けることがたくさんあるんですよね。将来に悩む若い人たちが多いんだな、と感じます。
多彩な進路があるうえ、社会がどう変化していくか読めない現代、進路に悩む人は増えていますよね。実際に私の目から見た中高生たちも、悩んでいる子が多いように感じられます。
そこで大阪国際中高では、自分の夢を宣言する「立志式」といったものに取り組もうと考えているんですよ。宣言したら必ずその道に進まなくてはならない、というものではなくて、まずは進みたい道を考えてみる、そんな取り組みができたらな、と。
それは良いですね。私は中学生の頃、何になりたいのかわからずモヤモヤとして過ごしていました。好きなものはあったけれど、将来に何がしたいのかわからない。そんな時期がありましたから、学校の取り組みとして「志を書く」というのは、良いことだと思います。
天野さんにも悩んだ経験がおありなんですね。ちなみに、電子工学の研究者になられた天野さんですが、小さい頃から理系に進みたいという気持ちがあったんですか?
全くなかったです。ただアマチュア無線※2が好きで、中学時代はずっと夢中になっていました。だからその気持ちが、ずっと今まで続いてきたのかな、とは思います。
あとは本が大好きだったので、中学の頃はたくさん本を読んでいましたね。当時は星新一さんが大好きで出版されている本は全部読んだぐらいです。
星新一さんの作品の、どんなところが好きでした?
SFの雰囲気と、「作者が何かを伝えようとしている」という裏のメッセージのようなものが感じられる部分ですね。
どこか社会の矛盾を訴えかけているような雰囲気が常にあって、それが子どもながらに、社会の見方を教えられているような気がしました。物事を横から見たり、斜めから見たりする必要があるんだよ、と。
今、中学時代を振り返ってみると、私は色んな知識や考え方を探し求めて、その中から何か「信頼するもの」を見つけようとしていたのかもしれませんね。
なるほど。本には様々な知識やアドバイスが詰まっていますからね。そうして見つけたものの中には、人として成長するチャンスがいっぱいあると私は思います。
それでは天野さんは、悩み抜いた中学時代の後、どのように進路を決めたんですか?
「好き」という気持ちに向かって行った、という形です。私は数学が一番好きだったので、高校から理系に進みました。
好きだ、という気持ちが原動力というのは良いですね。その後の進路に電子工学系を選んだ理由はなんですか?
実は、最初は電子工学系の学科ではなく、数学科に進みたいと考えていたんです。当時、京都大学に憧れの先生がいらっしゃって、その人に学びたいと思っていました。しかし、共通一次試験(現在の大学入学共通テストにあたる試験)で失敗し、「これでは数学で食べていくことはできない」と痛感して。進路を変えることに決め、就職で有利だと言われていた電子工学系に進みました。
そうだったんですね。決断されたとき、学校の先生やご両親に相談したりされたんでしょうか?
私は父に相談しました。相談した回数は多くなかったですが、話すたびにたくさんのアドバイスをくれて、とても有難かったです。そのときに教えてもらった「工学部は卒業後に色んな選択肢が持てるぞ」というアドバイスをもとに、大学を選びました。
天野さんは悩み、迷いながら進路を選んでこられた方なんですね。私も進路について、選択を迫られたことはありました。
私は中学の頃、英語が大好きだったんですが、高校以来、嫌いになってしまったんです。ずっと英語ができないまま過ごしていたのですが、父から「MBA※3を取得してアメリカで学ぶか、博士号を取りなさい」と言われたんです。いつかは自分の後を託したいという父の気持ちだったのでしょう。結局、私はMBAの取得をするためにアメリカへ渡ることになり、大嫌いだった英語も必死で学びました。
今では英語が大好きです。正直、人生は何が起こるかわからないものだとつくづく思います。
でも、自分が納得して選んだ道なら、自ずとひらけるものなのだと実感しました。
意外なエピソードですね! でも、確かにその通りだと思います。
物事をどう見るか、そしてどんな見方があるのか、さらにどう向き合うか。それを考えること、そしてそれを教えてくれる人と出会うことは、人生のターニングポイントになりますね。
大切なのは、人と向き合う姿勢。
進路に悩んだ中学時代、数学系への進学で挫折を経験した高校時代。それでもいつも、自分で考えて進む道を決めてきたことを話す天野氏。その後、選んだ道でどのような時間を過ごしてきたのか、研究者となってからの人生についてお話を聞いていく。

本学理事長:奥田
研究者の皆さまは、自分の仕事の成果が出るまで長い時間がかかることが多いですよね。天野さんにとって、研究を続けていくうえでのモチベーションは何ですか?
研究によって変わってきますね。
例えば、国や支援していただいている方から資金をいただいて進める研究の場合は、「支援してくださる方々の期待に応えよう」という気持ちがモチベーションになります。私たち研究者を信じてお金を出してくれた人たちに、成果を出すことを約束しているわけですから、力の入り方も変わりますね。そういった場合は、「信頼される人間になる」ことが第一であり、それが研究と向き合う原動力です。
一方、科研費といって「自由に使っていい研究費」があるのですが、そちらを使った研究の場合は、自分自身の好奇心が原動力になります。興味のあるテーマについて研究していると、新しいアイデアが生まれることは多いんですよ。それに、実験を重ねる中で少しずつ新しい発見をしていくのは、すごく楽しくてワクワクするんです。実験に成功するまで1,500回以上失敗し続けたこともありますが、失敗のたびに気づきがあって、それがまた楽しい。まぁ、いくらワクワクしても、夜中の12時を過ぎて研究をしていた日なんかは、クタクタになっちゃいますけどね(笑)
そういったように、様々な仕事の取り組み方ができるのは、ありがたい環境だと思っています。
一口に研究といっても様々な形があるんですね。 そもそも天野さんは、どうして青色発光ダイオードの研究を始められたんですか?
私は数学が好きだったので、計算機やコンピュータにすごく興味があり、最初はそういった方面の研究をしたいと考えていたんです。私が学生だった頃のスーパースターといえば、ビル・ゲイツをはじめとする敏腕起業家たちでした。彼らは、最初はプログラムを作って、それを企業に売り込みに行って……ということを繰り返して成功していったんですよね。だから私も、憧れの存在がそうしていたように、コンピュータの分野の仕事をしてみたいと思ったんです。ただ、進学先の大学にはその分野の研究室がなくて……。
どうしようかと考えていたとき、ともにノーベル賞をいただいた赤﨑勇先生にお会いしたんです。赤﨑先生は様々な分野の研究をされていて、当時から青色発光ダイオードの研究もなさっていました。その研究を拝見したときに、とても面白そうだと感じて、赤﨑先生に師事し始めたんです。
なるほど。人との出会いの中で、道が見つかったんですね。それがやがてノーベル賞受賞まで続くことになるとは、なかなかすごい御縁です。
赤﨑先生がいなかったら、青色発光ダイオードの研究もやっていなかったと思います。素晴らしい恩師がいてくれたというのは、とてもラッキーなことでした。まあ、私は赤﨑先生に褒められたことはないんですが(笑)
それは驚きですね! すごく厳しい方だったんですか?
いえいえ。外部の方には厳格な先生に見えたかもしれないですけど、とても優しい方でしたよ。それに、話し始めると止まらない方でした。だいたい話し始めると平均して2~3時間は喋っているような方でしたね。お話好きで。
お茶目な一面もある方だったんですね。天野さんも明るくて、人を引き込む雰囲気がありますよね。先ほど「信頼される人間になる」という話もいただきましたが、研究者として働くうえで「人間性」というのはやはり重要ですか?
とても大事なことです。 私は今も現役で研究を行っていますが、研究を任されたときは「信頼できる人間になる」というのを目標にしています。実は私は昔から人と話すことが苦手なのですが、仕事のときは頑張って話そう・伝えようと心がけているんです。
ただ年齢を重ねるうちに、目標にすることが少し変わってきました。最近は「いかに若い人に元気になってもらうか」と意識するようになっているんです。そのための環境を作る必要があるし、研究を楽しめる気持ちになってもらうことが大事だな、と考えるようになってきました。
今までは「自分が研究を頑張る!」という気持ちが強かったんですが、今はそれよりも「いかに若い人たちに頑張ってもらうか」ということを考えるように変わってきましたね。
いつまでも「やりたいこと」を求める心を。
恩師・赤﨑勇先生との出会いから始まり、研究者としてノーベル賞受賞まで大成していった天野氏。その研究に対する熱意は、「信頼される人間になる」という誠意と、「やりたいことを楽しむ」という好奇心から生まれていた。最後に、そんな天野氏から悩みながら未来へ向かう生徒の皆さんへメッセージをいただく。
天野さんは、進路に悩みながらも「好き」を大切にして道を選び続けたんですよね。当時の自分のように迷っている生徒がいたら、どんなことを伝えたいですか?

名古屋大学教授 天野浩氏(2014年ノーベル物理学賞受賞)
目指すものは何でも良い、ということです。本当にのめり込めることをやりなさい・見つけなさい、それが人生なんだよ、と伝えたいですね。
私の恩師の赤﨑先生も、「自分のやりたいことをやりなさい」と、いつもおっしゃっていました。逆に言えば「やりたくないことはやらない」ということなんですけどね。ワガママなところもある先生だったんですよ(笑)
でもそれでいいんじゃないかと思います。やっぱり、やりたくないことをやるときに必要なエネルギーは、やりたいことに熱中にしているときのものと比べると、だいぶ違いますから。
どれだけ困難な状況でも、やりたいことをやっていると楽しい。インタビュー等でそう答える方も多いですよね。
安定した企業に勤めて安全に暮らしていくことを目標にするのも一つの選択ですが、何事も恐れず、自分が納得できる道を模索する心も、子どもたちには持ってほしいと思います。
安定を選ぶかどうか、というお話では、私にもかなり悩んだ時期がありました。
私はマスター※4を取得するか、ドクター※5取得まで頑張るか、悩んでいました。ドクターなら研究者としての活躍の場が海外まで広がりますが、マスターでも十分仕事はあります。定年まで安定して暮らすことを第一に考えていたら、マスターを選んでいたかもしれません。
そのとき赤﨑先生がドクターの道を勧めてくださったんです。そのおかげで私はノーベル賞受賞者の1人として名前を連ねることができました。
選択はもちろん、人それぞれです。でもその選択に後悔しないように、様々な可能性を考えて挑戦するべきだと思います。
なるほど、とても良いお言葉です。今はコロナ禍と直面し、色々な制限がある時代となってしまいましたが、その中でも子どもたちがたくましく成長して社会に羽ばたくためには、そういった心意気が重要だと思います。私たちも、子どもたちが前を向けるように全力でサポートしていきたいです。
教育者の方の存在は、これからますます大切になっていくと思いますね。
私は小さい研究室を持っていて、大学院生たちと研究をしていますが、昔は学生に何か伝えたいことがあったとき、メールを出すだけだったんです。でも今は一人ひとり顔を見ながら話をすることを心がけています。
そうすることで、だいぶ学生の気持ちが変わってきたと感じます。自分で考えて積極的に実験へ取り組んでくれるようになったな、と。
そういった、顔を見ながら1対1で一人ひとりと向きあうということが、これからの中学・高校ではますます大切になってくるんじゃないか、という気がしています。
だから「君が大切なんだよ」というメッセージを出し続けるということは、教員の皆さまにぜひやっていただきたいです。応援しています!
ありがとうございます。生徒とともに、私たち教員も「今、求められるもの」を探し続け、挑戦していきたいと気が引き締まりました!
生徒一人ひとりと教員が向き合い続けるのはもちろんですが、人と協働し、ともに歩んでいく姿勢を、生徒たちに養っていきたいと思います。
確かに、コロナ禍の影響で対面でのコミュニケーションやグループワークの機会も減っていますから、改めて「協働する姿勢」を教育で意識することは大事なことですね。
私がノーベル賞を受賞したときの話なんですが、ノーベル賞の受賞者は「ノーベルウィーク」といって、2週間ほど海外の様々な行事に招待してもらえるんです。そのとき、スウェーデンの高校の授業を見学する機会がありました。
そこで印象的だったのが、普段の授業もディベート形式で実施していたことです。数学の授業でも、いくつかのグループに分かれて問題を解き、答え合わせをする前にそれぞれのグループが「自分たちはどのような根拠から解答を導き出したか」を発表し合っていました。
こういった取り組みをしていれば、考える力・発信する力をしっかりと伸ばせるだろうな、と思いましたね。そして、中学・高校ではそういった取り組みを積極的に行うと、社会に出たときにとても役立つ力が身につくんじゃないか、と思いました。
新しくやりたいこと・好きなことを見つけて挑戦し始めるのは、いつになっても全然問題ないと思うんです。大事なのは、それを求める姿勢と自分の意志。私も本当に好きなことを見つけたのは、22歳のときですしね。
やりたいと思うことを、ずっと探し続けたらいいんですよね。そして悩み続けること自体も、楽しんだらいい。
それは良いですね!
私は61歳になったんですが、「来年から何をしようかな?」と今も考えています。まだまだ、色んなことにワクワクしていきたいです。
※1シンポジウム:公開討論会のこと。発表者と聴衆に分かれて行う討論会。一つの課題に対して数人の発表者が意見を出し合い、それを聴衆から質問を行う形で進行する。
※2アマチュア無線:個人的な趣味として、トランシーバといった通信道具を自分で組み立てること。
※3MBA:経営学修士。経営者や経営をサポートするビジネスプロフェッショナルを育成するためのプログラムを学んだことを証明する資格。
※4マスター:修士号。大学院博士課程(前期課程または修士課程)で2年間研究し修了時に授与される学位。
※5ドクター:博士号。大学院博士課程(後期課程)で研究し、一定の成果を上げることで授与される学位。
もくじ
- 対談9
株式会社プリローダ/日本農業株式会社:大西千晶氏
心で感じ、行動しよう。動かなければ何も生み出せないから。 - 対談8
外交官:吉川元偉氏
語学を学べば世界が広がる。好きなことをモチベーションに学んでほしい。 - 対談7
作曲家:新実徳英氏
曲がりくねって進んでも、好きだから努力できる。 - 対談6
アサヒビール株式会社
専務取締役マーケティング本部長:
松山 一雄氏
「点」はいつか、きっとつながる。 - 対談5
TMI総合法律事務所代表:田中 克郎弁護士
人は、人との交流の中で育つ。たくさんの出会いを経験しよう。 - 対談4
モンベルグループ代表・登山家:辰野 勇氏
自分の「好き」へ進み続けること、それは未来の糧となる。 - 対談3
名古屋大学教授 天野 浩氏
(2014年ノーベル物理学賞受賞)
未来に向かう子どもたちへのメッセージ、やりたいことに挑戦する道を進もう。 - 対談2
森永製菓株式会社 取締役常務執行役員:宮井真千子氏
次の世代の子どもたちに伝えたい、好奇心と挑戦が未来を拓く。 - 対談1
株式会社パソナグループ代表:南部靖之氏
少子化時代の未来を創る子どもたちに贈る人生を輝かせる言葉。