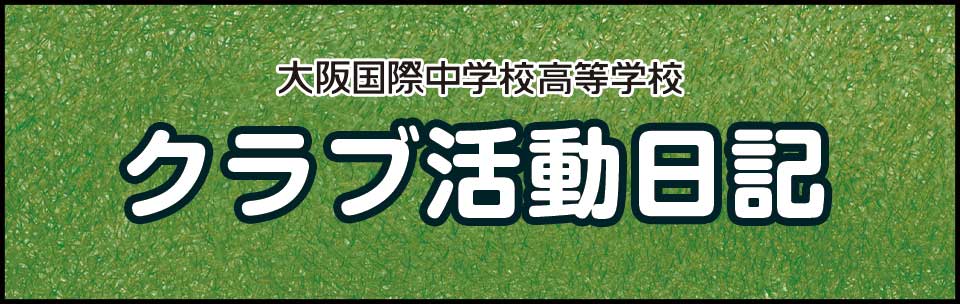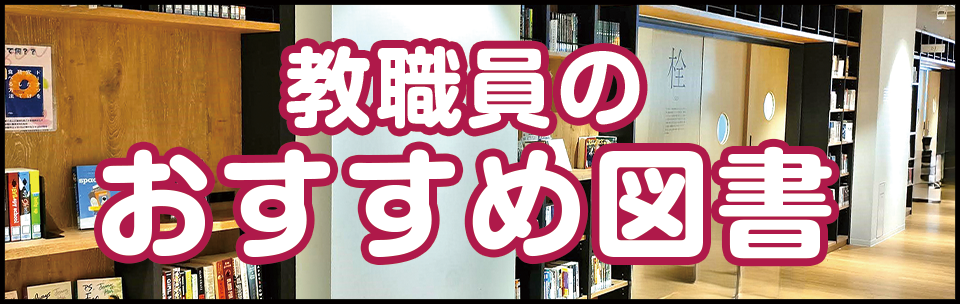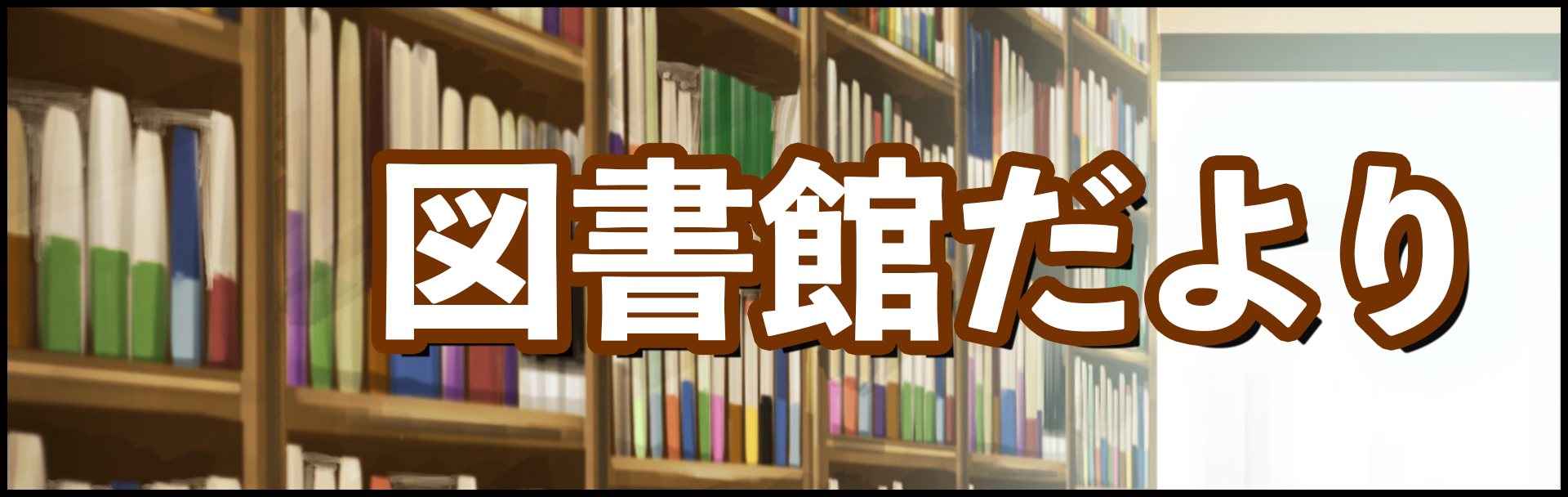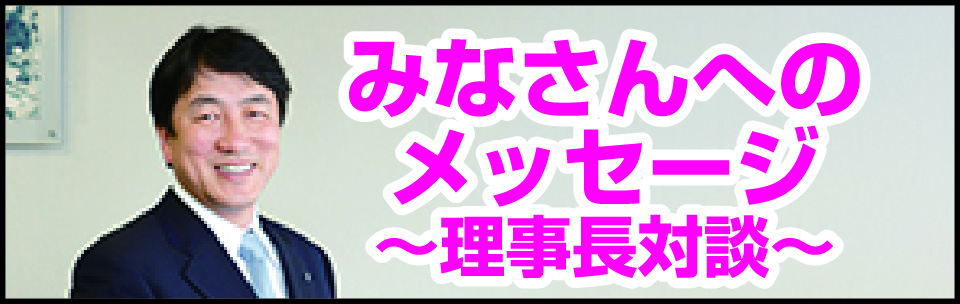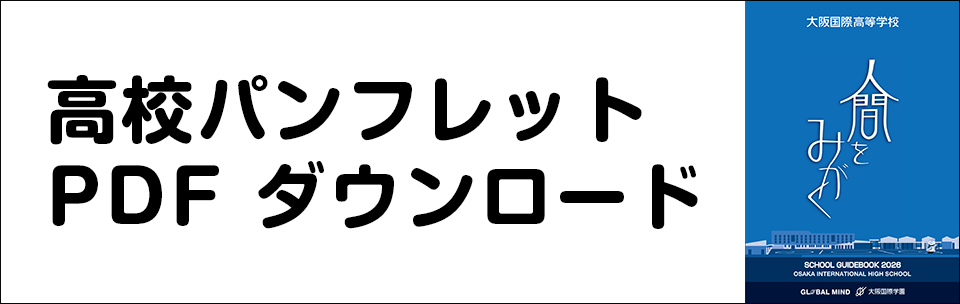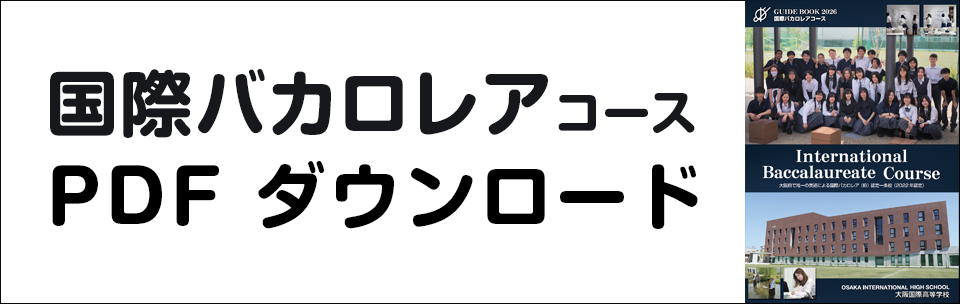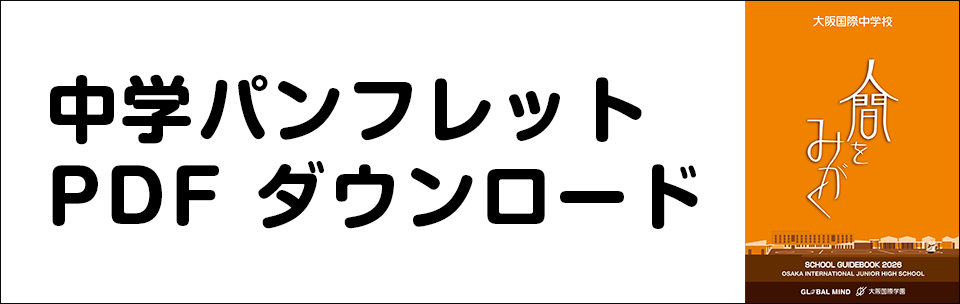中学生の男子が校内で捕まえたというニホンヤモリ(以下「ヤモリ」)を持ってきてくれました。授業で教室に持って行き、生徒に見せると、「かわいい!」という感想も結構ありました。キョロッとした眼がどこかネコの眼を思わせるところもあり、しかも大人しい。近年はは虫類をペットにする人達も増えていると聞きますが、頷ける話です。
紀元前4世紀、アリストテレスはヤモリを観察し、「どんな体勢でも、たとえ頭を下にむけていても、木を駆け上ったりおりたりできる。」と記述しているといいます。昆虫が垂直な壁や天井に止まっていたり、タコが強い力で岩にしがみついていたりするのを何の気なしに見ていますが、ヤモリが垂直な壁面にピタリと止まることができるしくみは非常にユニークで、そのしくみが理解されたのは何と2000年になってからなのです。ツメや吸盤でつかまってとるのでもなく、粘着物質を分泌しているのでもなく、「ファンデルワールス力」で吸着しているということが明らかになりました。
【問題】ファンデルワールス力とは? (高校の化学で学習しますね。)
ヤモリの足の指先に注目してください。吸盤でもなければ、粘着物があるわけでもありません。ただ指に対して横方向にあるヒダが目につきます。これを電子顕微鏡で観察すると指には1平方メートル当たり10万から100万本もの毛がえており、その先端はさらに直径100ナノメートルほどの細かい毛に分かれています。この構造はさまざまな形状をした表面にピタリと合致するとともに、そこにファンデルワールス力という分子どうしが引き合う力が生じます。(ファンデルワールス力そのものの説明は省略させてもらいます。ごめんなさい。)分子間に生じるさまざまな力の中で、実はファンデルワールス力それほど大きな力ではありません。しかしナノサイズの毛に生じた力を結集することでヤモリは体を支えることができるというのです。
2つの物質を接着させることついて、ヤモリの足の表面の知見は新しいアイディアを実用面にもたらしました。ロボット工学の研究者はヤモリの足を模倣したロボットを作成し、従来のロボットがいけなかった垂直面に到達し、なおかつ長時間留まることを可能にしたそうです。また2012年には日本のある企業が、従来の粘着テープとは異なり、剝がしても跡が残らず、繰り返し使用できる「ヤモリテープ」を開発したとか。
アリストテレスが注目し、そのしくみが現代になって解明され、そして私たちの暮らしへの応用される―生きものたちから学び取ることはまだまだたくさんあると改めて実感します。
参考文献:実教出版 理科資料78号「なぜヤモリは壁にはりついて歩けるのか」
東京大学大学院教授 平岡秀一
【キーワード】ファンデルワールス力 ナノサイズ